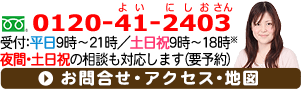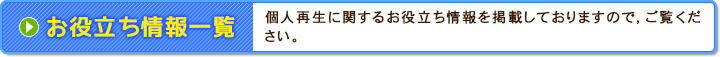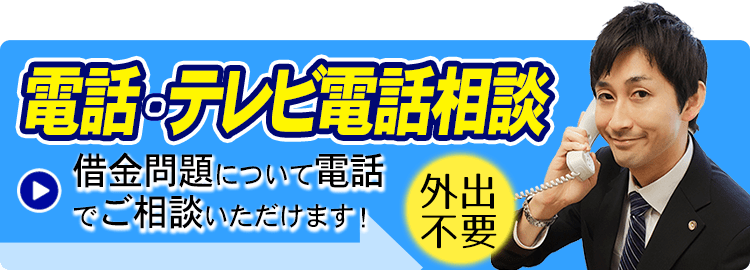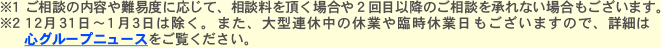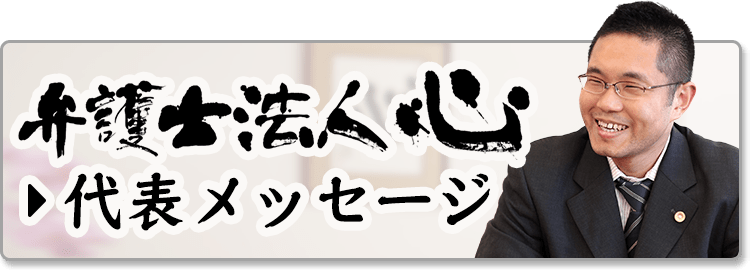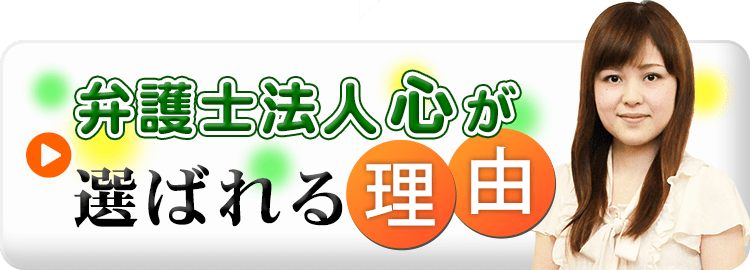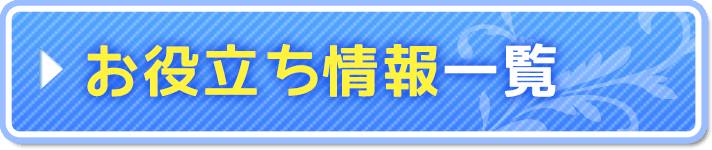Q&A
個人再生ができないケースというものはありますか?
1 個人再生をすることができないケースについて
個人再生は、いくつかある債務整理の方法の中でも比較的複雑なものであり、手続きを用いるためには厳格な要件を満たす必要があります。
次のようなケースにおいては、個人再生ができないことがあります。
①債務総額が少なすぎる、または多すぎる
②個人再生後に再生計画に従った返済ができない可能性がある
③一定の債権者が再生計画に反対する
④個人再生に必要な費用が用意できない
以下、それぞれについて説明します。
なお、個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがありますが、本稿では実務上利用されることが多い小規模個人再生を前提とします。
2 債務総額が少なすぎる、または多すぎる
個人再生は、債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きですが、債務総額を100万円以下にすることはできません。
債務総額がもともと100万円以下である場合には、個人再生をしても、分割支払いや損害金等を除き、意味がないことになります。
逆に、債務総額が5000万円を超える場合(住宅ローンを除く)も、個人再生を利用することはできません。
債務総額が5000万円を超える場合には、原則的な手続きである民事再生手続きが適用されます。
3 個人再生後に再生計画に従った返済ができない可能性がある
これには、いくつかのパターンがあります。
1つめは、継続的に安定した収入が得られる見通しがない場合です。
個人再生をすると、再生計画に従って、減額後の債務を原則3年間で分割返済をすることになります。
安定した収入がないと、分割返済ができないと判断され、再生計画が認可されない可能性があります。
2つめは、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)に対して、減額後の債務額が大きすぎる場合です。
これは、さらに細かく2つのケースに分けられます。
まず、債務総額が大きいケースです。
例えば、債務総額が4000万円である場合、個人再生をしても最低400万円を3年間で分割返済する必要があります。
ひと月あたりの返済額は11万円を超えますので、毎月12万円程度の返済原資を用意できない場合には再生計画が認可されません。
次に、債務者の方が保有する財産の評価額が高額である場合です。
個人再生には、債務者の方が保有する財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在します。
仮に債務総額が1000万円である場合、最低弁済額は200万円です。
しかし、保有財産の評価額が400万円である場合には、再生計画認可後に400万円を返済しなければなりません。
この場合も、毎月12万円程度の返済原資を用意できない場合には再生計画が認可されません。
4 一定の債権者が再生計画に反対する
小規模個人再生の場合、債権者の頭数の半数以上が再生計画に反対した場合か、反対をした債権者の債権額が債権総額の半額を超える場合には、再生計画が認可されません。
このような展開になることが予想される場合には、給与所得者再生を検討することもあります。
5 個人再生に必要な費用が用意できない
個人再生を裁判所に申し立てる際には、申立ての手数料のほか、裁判所に納める郵券(切手)代や官報公告費が必要となります。
これは、一般的には2~3万円程度です。
弁護士に個人再生を依頼する場合には、30~50万円程度の弁護士費用が必要となります。
また、個人再生申立後に再生委員が選任される場合には、15~20万円の再生委員報酬が必要となります。
これらの費用が用意できない場合、現実的には個人再生をすることはできません。
実務上は、弁護士に個人再生を依頼した場合には、個人再生後の想定返済額を毎月積立てて弁護士費用等に充てるということが多いです。
債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか? 個人再生をする場合、引っ越しをすることはできますか?